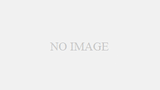ここでは条件分岐の1つであるswitch文を使ってみましょう。
if文 の親戚みたいなものです。
動かしてみよう
では、サンプルコードを動かしてみましょう。
入力値が1,2,それ以外のどれかを表示するプログラムです。
入力欄へ数字を入れた後、実行ボタンを押してください。
解説
switch文の基本的な構文は下記のとおりです。
switch( 変数 )
{
case 定数1:
処理1;
break;
case 定数2:
処理2;
break;
default:
処理デフォルト;
break;
}
switch部分に書かれた変数が定数1なら処理1をやる、というような動作をします。
該当する定数がなかった場合には、defaultに記述された処理をおこないます。
if文との比較
先に示した基本構文をif文で表現すると下記になります。
if( 変数 == 定数1) { 処理1; }
else if( 変数 == 定数2) { 処理2; }
else { 処理デフォルト; }
switch文で実現できる処理はif文でも書けます。
しかし、逆は成り立ちません。
switch文は場合分けに特化したif文の親戚だと思えばよいでしょう。
注意点
break忘れ
switch文では下記のように case の break を書かない記述もできます。
switch( 変数 )
{
case 定数1:
処理1;
case 定数2:
共通処理;
break;
default:
処理デフォルト;
break;
}
上記の場合、変数が定数1の時に処理1と共通処理が実行されます。
意図的に使う文には便利ですが、breakの書き忘れによってこのようなソースコードを作ってしまうミスが多いです。
気をつけましょう。
default忘れ
defaultケースは省略可能ですが、基本的には書いた方がよいです。
何も処理しない場合には何もしないことをコードとして明記しておいた方が安全です。
まとめ
まとめです。
- switch文によって条件分岐が作れます。
- if文でも同じことができます。
- breakを忘れないようにしよう。
- defaultは書くようにしよう。
以上です。
ではまた。