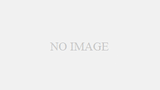ここでは標準的な入出力に多少慣れておきましょう。
というのも、今後の実践を進めるにあたり、「何かを入力→結果を確認」というシーンが多くあるからです。
動かしてみよう
ということで、サンプルコードを用意しました。
とりあえず動かしてみましょう。
入力欄になにか数字をいれた後に、実行ボタンをぽちっと押してみてください。
入力した数字が出力欄に表示されましたか?
前回(こんにちは、世界。)は、ソースコード中に書いた文字を出力する練習をしましたが、今回は一歩進んで、入力された数字を出力してもらいました。
入力された数字や文字を扱えるようになることで、プログラムに対話的な動作をさせることができるようになるため、プログラムの幅が広がります。
解説
では、続けて解説に進みます。
#include <stdio.h>
これは「stdio.h を使わせてね。」という意味でした。
サンプルコードで使っている、scanf機能とprintf機能は両方ともstdio.hの中に収納されているので、このinclude記述が必要となります。
次の行ですが、
int main(void)
{
}
これはメイン関数でした。
C言語で書かれたプログラムはこのメイン関数を上から実行する形で処理が進みますので、必ず必要な記述でした。
次の行です。
int input;
これは「inputという名前の変数(数字などをいれる箱)を作ります。」という意味です。
ここでは input という名称にしていますが、a とか b とか suuji などの違う名称も使用できます。
変数についての詳細は別ページにて説明しますので、のちほどそちらもご覧ください。
次の行ですが、
scanf("%d", &input);
これは初めて出てきた記述ですね。
この記述によって、入力欄に記入された数字をプログラムの中に取り込んでいます。
「入力欄に書かれた数字を input の中にいれる。」の認識でいいです。
なお、inputの頭には & をいれる必要があります。
詳しく知りたい場合には、ポインタについて学ぶ必要がありますが、現時点での認識としては「&を書くことになってるんだなぁ。」ぐらいで支障はありません。
最後は下記です。
printf("%d が入力されました。", input);
前回(こんにちは、世界。)とやや違う記述になっていますね。
printf機能には様々な使い方が規定されていて、変数を表示させる場合の一例が上記です。
以上により、入力欄に入れた数字が出力欄に表示されるという機能が実現されています。
まとめ
本ページのまとめです。
- 基本的な入出力の使い方について学びました。
- scanf機能により、入力を受け取れることを学びました。
以降、バンバン使いますので、覚えておいてくださいね。
以上です。ではまた。